![]()
| 阿山町・阿山町観光協会 Tel 0595−43−0334 Fax 0595−43−1679 〒518-1395 三重県阿山郡阿山町大字下馬場1128番地 |
 緑の深いグランデーションに包まれた阿山のまち。山々に息づく木々、田に広がる稲、こkでは風までもがほんのりと優しい緑色の香りをおびているようです。大自然の中でのキャンプや乗馬、乳しぼり、様々な体験教室等を阿山の人々とのふれあいと共に楽しんでください。
また、阿山町の歴史と文化を肌で感じることができる。伝統ある祭りや神事の数々も今に伝えられています。
豊かな自然や文化を守り、人にも自然にも優しい阿山町播、町そのものが、『エコ・ミュージアム』。緑の中にやすらぎの時が流れる町です。 緑の深いグランデーションに包まれた阿山のまち。山々に息づく木々、田に広がる稲、こkでは風までもがほんのりと優しい緑色の香りをおびているようです。大自然の中でのキャンプや乗馬、乳しぼり、様々な体験教室等を阿山の人々とのふれあいと共に楽しんでください。
また、阿山町の歴史と文化を肌で感じることができる。伝統ある祭りや神事の数々も今に伝えられています。
豊かな自然や文化を守り、人にも自然にも優しい阿山町播、町そのものが、『エコ・ミュージアム』。緑の中にやすらぎの時が流れる町です。 |
| ●伊賀焼 | |||||
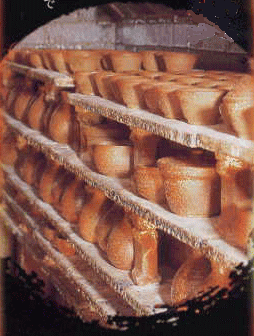 ◆伊賀焼1200年の歴史 ◆伊賀焼1200年の歴史 伊賀焼のはじまり 伊賀焼の歴史は古く、奈良時代までさかのぼります。平安時代末期から鎌倉時代の始めごろに本格的なやきものの産地として発展し、室町時代の終わりから桃山時代にかけて侘び茶が広まると、個性的な伊賀焼きは茶の道具として注目されるようになりました。領主として伊賀国を治めた筒井定次や藤堂高虎が茶人であったことから、伊賀焼は、茶の湯のセンスや心遣いを巧みに取り入れていきました。 土の風合いと、炎による変化が生み出す自然な「景色」。整った形に手を加えることによって生まれる、より自由でおおらかで生き生きとした形・・・「破調の美」。 伝統の力とともに 伊賀焼は江戸中期に一時衰退しましたが、18世紀中ごろに京都や瀬戸から技術者を招き、伊賀の土を活かした日用雑器の生産が行われるようになり、現在の基礎が作られました。 現在の伊賀焼は阿山町の丸柱を中心に焼かれています。製品は、土鍋や行平、食器や茶陶など多岐にわたり、また、伝統を生かした新製品の開発も行われてります。 阿山の豊かな自然の中で、こつこつと堅実に作られつづけてきた伊賀焼には、茶陶から受け継がれた、使う人への心遣いと、良いものを創りつづけていきたいという阿山の心意気が息づいています。 |
|||||
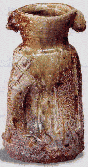 |
◆伊賀焼の特徴 | ||||
| 素朴で、無骨で、頑固者。 しかし愛すべき伊賀焼たち。 伝統を守り続けてきた強さと、 使う人へのやさしさを秘めた 伊賀焼の特徴をご紹介。 |
|||||
| 灰かぶり・焼締め・ビードロ 振りかかった薪の灰が、高温の炎の中で溶かされる。あるいは流れて緑色の雫となる。すさまじい炎の力に飾られた無釉焼く締めのつわものの顔。 |
無釉焼締めの肌合い 伊賀の大地そのままの小石まじりで一見無骨な面構え。そのくせ料理は美味しく、酒は旨く。心配りの引き立て上手。素朴でやさしい恥ずかしがり屋。 |
| 山割れ・ゆがみ・耳 大きな山割れ、豪快なゆがみ。ヘラ目を施し、「耳」を付ける。整った形に手を加えた破調の美。より自由でおおらかな、日本人独自の美意識を秘めて。 |
火色・こげ 炎にあぶられた色白の顔が燃えさかるその色を映して赤く染まる。あるいは焦げる。ビードロあり、こげあり、火色あり。炎が描く千変万化のこの表情。 |
| ●観光 | |||
 |
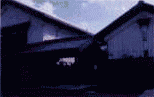 |
 |
|
| モクモク手づくりファーム | 陶芸体験教室 | ふるさとの森 | |
伊賀の国
| ●祭り・イベントスケジュ−ル | |||
| 2月 | 18日 | だだ祭り 夜に裸の男たちが肩を組んで押し合いをする。「だだ」は「裸裸(らら)」がなまった言葉といわれ、厄払いや五穀豊穣を願い、江戸時代から神社に伝わる奇祭 |
陽夫多神社 |
| 4月 | 18日 | 春祭(能奉納) 江戸時代に金春流の能師喜左衛門が伊勢神宮への参拝途中、槙山で病気を患ったが、郷人の手厚い看護によって治った伝えられる。以来、病気平癒願ほどきに能が奉納される。 |
真木山神社 |
| 4月 | 20日 | 春祭(鞨鼓踊り奉納) 町指定無形文化財。五穀豊穣、雨ごいの神事として寛永年間に始まったとされる。古くは大江地区の火明神社で行われたが、明治41年の合祭から陽夫多神社の行事となった。 |
陽夫多神社 |
| 7月 | 第4 土・日 |
伊賀焼陶器まつり 1250年の歴史を誇り、国の伝統工芸品に指定されている「伊賀焼」の展示即売 |
すぱーく阿山 あやまふれあい公園内 |
| 8月 | 1日 | 祇園祭(願之山踊り奉納) 町指定無形文化財。病気完治、家内安全の願かけを解く神事で、文禄元年間に始まったとされる。 |
陽夫多神社 |
| 10月 | 17日 | 秋祭(奉納花火大会) ここの奉納花火は「願火」と呼ばれ、伊賀流忍者の狼煙が発祥と伝えられる。約350発の花火奉納 |
手力神社 |
| 11月 | 20日 | けんずいまつり 「あやまの恵み・食・文化」をテーマに各種イベント、町特産物展示即売会、バザー等の催し物 |
あやまふれあい公園内 |