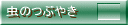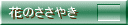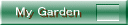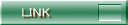| <はじめに> |
| 三重県名張市内の主だったハッチョウトンボの生息地は、市内の端々に点在する湧き水のある、極浅い水深の小規模な休耕田です。 しかし、山あいにある小規模休耕田は、所有権が複雑に入り組むこともあり、保存への働きかけが簡単には進まないという難点を抱えています。 ここ2~3年の間に最大規模の生息地を立て続けに2箇所絶滅させてしまうなど、「ハッチョウトンボを守る会」の活動も挫折の一途をたどってきました。 あるときは、ヤゴを代替地に移す計画を立てながら、移転先の整備が進まなかったり、開発のための重機が入る直前になっても生息地の持ち主の在住地さえ把握できないという手際の悪さがあったりもしました。その結果、一昨年には、主だった貴重な生息地を2箇所立て続けに失なうことになってしましました。 その後、20002年7月。ふとした事から自宅に程近いささやかな休耕田にハッチョウトンボ♂1匹を確認しました。♀を未確認、不安を抱いたまま2003年、今年の5月。幸運にも♀を含め総個体数6匹の生息をを確認することができました。 すぐ横の山林が、整備されるに伴いこの湿地の存続も危ぶまれてきましたので、生息地リポートとして、、密やかに・凛と生きる命の美しさの一端でもご紹介いできればと思うのですが・・・。 |
| トンボ科ハッチョウトンボ属 Nannophiya pygmaea |